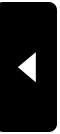2020年11月29日
私はいつも星に向かって飛んできた♪
こんにちは。
今日は私が最近読み直している本からのご紹介です。
本は、「勝利への軌跡 ポール・J・マイヤー」(著/グラディス・ハドソン)です。ポール・J・マイヤー氏のことは、ご存じの方もおられるかも知れませんが、SMIという自己啓発プログラムの創設者で、プロフィールは下記のとおりです。
☆ポール・J・マイヤー プロフィール
ポール・J・マイヤー(1928年-)は、アメリカの自己啓発作家、教育家。カリフォルニア州サンマテオ出身。保険のセールスマンとして大きな成功を収め、1951年に最年少で MDRT(Million Dollar Round Table)のメンバーとなる。1960年に自身の成功哲学を体系化・システム化しSMI(サクセス・モティベーション・インスティテュート)を設立。マイヤーの自己啓発プログラムは世界80か国以上活用され、高い評価を獲得している。
私も若き日に、SMIプログラム(カセットテープ版)を購入して勉強し、その時この本も買って読みました。出版年月を見たら1986年7月となっていましたので、私が20台半ばの頃に買ったようです。最近ふとまたこの本が読みたくなって、読み直していたところ、次のような下りがありました。
「最近一人のハンサムな24歳の青年が私に言った。『私はいつも星に向かって飛んできた。それが山の頂上に到る一番いいやり方だということがわかったからです。もしあなたがほしいものについてあなたの考えを結晶化すれば、あなたは人生で欲しいものは何でも手に入れることができます……あなたはプランを作ることが必要です』と、こうフロリダの航空会社担当部門の新しい写真は伝えている」
(「勝利への軌跡 ポール・J・マイヤー」 p.80から抜粋)
この24歳の青年が、ポールのことです。文中の「私はいつも星に向かって飛んできた。」という言葉が、いつのまにか私の人生観の一つになっていたらしく、私のブログの名称になっていたことに、今回気がついた次第です。
最初にこの本を読んでから、幾星霜を経て現在に至りましたが、未だ山の頂上にはほど遠いところにいる自分に気がつきます。でも、だからこそ、生涯現役で頑張るぞ!という気概を持って毎日を送れるのだとも思います。
ということで、今週もまた、星に向かって飛んで行こうと思います。ガンバ p(^^)q。

今日は私が最近読み直している本からのご紹介です。
本は、「勝利への軌跡 ポール・J・マイヤー」(著/グラディス・ハドソン)です。ポール・J・マイヤー氏のことは、ご存じの方もおられるかも知れませんが、SMIという自己啓発プログラムの創設者で、プロフィールは下記のとおりです。
☆ポール・J・マイヤー プロフィール
ポール・J・マイヤー(1928年-)は、アメリカの自己啓発作家、教育家。カリフォルニア州サンマテオ出身。保険のセールスマンとして大きな成功を収め、1951年に最年少で MDRT(Million Dollar Round Table)のメンバーとなる。1960年に自身の成功哲学を体系化・システム化しSMI(サクセス・モティベーション・インスティテュート)を設立。マイヤーの自己啓発プログラムは世界80か国以上活用され、高い評価を獲得している。
私も若き日に、SMIプログラム(カセットテープ版)を購入して勉強し、その時この本も買って読みました。出版年月を見たら1986年7月となっていましたので、私が20台半ばの頃に買ったようです。最近ふとまたこの本が読みたくなって、読み直していたところ、次のような下りがありました。
「最近一人のハンサムな24歳の青年が私に言った。『私はいつも星に向かって飛んできた。それが山の頂上に到る一番いいやり方だということがわかったからです。もしあなたがほしいものについてあなたの考えを結晶化すれば、あなたは人生で欲しいものは何でも手に入れることができます……あなたはプランを作ることが必要です』と、こうフロリダの航空会社担当部門の新しい写真は伝えている」
(「勝利への軌跡 ポール・J・マイヤー」 p.80から抜粋)
この24歳の青年が、ポールのことです。文中の「私はいつも星に向かって飛んできた。」という言葉が、いつのまにか私の人生観の一つになっていたらしく、私のブログの名称になっていたことに、今回気がついた次第です。
最初にこの本を読んでから、幾星霜を経て現在に至りましたが、未だ山の頂上にはほど遠いところにいる自分に気がつきます。でも、だからこそ、生涯現役で頑張るぞ!という気概を持って毎日を送れるのだとも思います。
ということで、今週もまた、星に向かって飛んで行こうと思います。ガンバ p(^^)q。

2020年04月19日
ショーン・エイカーの「20秒ルール」 ♪
こんにちは。
コロナ終息の目処がなかなかつかず、先の見えない日々が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私も仕事量が減って、時間が取れるようになったので、その時間で色々な本を読んだり、自宅の書斎やスタジオのオフィスの片づけをやったりしています。
そんな中、メンタリストDaiGoという人が書いた、「片づけの心理法則」という本に巡りあい、大変良い刺激を受けています。今日はその中からひとつご紹介させて頂きます。
それは、「20秒ルール」というもので、ハーバード大学の心理学者、ショーン・エイカー氏が『幸福優位7つの法則』という本の中で紹介したものだそうです。
☆心理学者ショーン・エイカーの「20秒ルール」
人間は、とりかかるときに必要な時間を20秒短縮するだけで、それを習慣化できる。
逆に、20秒余計に時間がかかるようにするだけで、習慣をやめられる。
つまり、 新しいことを習慣化したいのであれば、その習慣を実行するまでにかかる時間を20秒早めること。悪い習慣をやめたいのであれば、その習慣を始めるまでの時間を20秒だけ増やすということです。
私は子供の頃から、なかなか勉強に取りかからない一夜漬けタイプの子で、いまでもその悪習慣が抜けないでいます。今頃になってこの「20秒ルール」を知っても、少々手遅れっぽい感もありますが、「良いことを始めるのに遅すぎることはない」と自分に言い聞かせて、これからの人生に取り入れようと思います。
コロナ終息はいつになるか分かりませんが、終息して新しい世界の幕が開いた頃にはこの「20秒ルール」を体得して、自分の人生を最大化し、実り多きものにしたいと思います。最近、その手応えを感じ始めています。
ということで、今週も頑張ります(^^)v

コロナ終息の目処がなかなかつかず、先の見えない日々が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私も仕事量が減って、時間が取れるようになったので、その時間で色々な本を読んだり、自宅の書斎やスタジオのオフィスの片づけをやったりしています。
そんな中、メンタリストDaiGoという人が書いた、「片づけの心理法則」という本に巡りあい、大変良い刺激を受けています。今日はその中からひとつご紹介させて頂きます。
それは、「20秒ルール」というもので、ハーバード大学の心理学者、ショーン・エイカー氏が『幸福優位7つの法則』という本の中で紹介したものだそうです。
☆心理学者ショーン・エイカーの「20秒ルール」
人間は、とりかかるときに必要な時間を20秒短縮するだけで、それを習慣化できる。
逆に、20秒余計に時間がかかるようにするだけで、習慣をやめられる。
つまり、 新しいことを習慣化したいのであれば、その習慣を実行するまでにかかる時間を20秒早めること。悪い習慣をやめたいのであれば、その習慣を始めるまでの時間を20秒だけ増やすということです。
私は子供の頃から、なかなか勉強に取りかからない一夜漬けタイプの子で、いまでもその悪習慣が抜けないでいます。今頃になってこの「20秒ルール」を知っても、少々手遅れっぽい感もありますが、「良いことを始めるのに遅すぎることはない」と自分に言い聞かせて、これからの人生に取り入れようと思います。
コロナ終息はいつになるか分かりませんが、終息して新しい世界の幕が開いた頃にはこの「20秒ルール」を体得して、自分の人生を最大化し、実り多きものにしたいと思います。最近、その手応えを感じ始めています。
ということで、今週も頑張ります(^^)v

2013年01月20日
夢がかなう人の机はなぜ美しいのか?
皆さん、こんにちは。
今日は久しぶりに「仕事術」についての記事です。
お正月に本屋にブラリと行って、ふと目にとまった本。書名は「たった1分で人生が変わる。片づけの習慣」で、パラパラとめくってすぐにそのまま買いました。
私は片付けが苦手で、すぐに書類が溜まってしまって捜し物をする羽目になることが多いので、「超整理法」(野口悠紀雄著)とか、「掃除道」(鍵山秀三郎著)などの本を読んで、できることはやってきたつもりでした。
それでも昨年の暮れからお正月にかけて、結局デスクの上は片づけられないまま新年を迎えて、つい先日必要に迫られて片づけた位です。そんな私にピッタリの本だと感じました。内容は単なる整理法の羅列ではなく、「片づけ」というものが、そのまま人生の夢の実現にも大きく影響を与えるという観点から書かれていましたので、このブログのテーマ「夢の実現」にそのまま当てはまると思い、皆さんにもご紹介させて頂くことにしました。分かりやすくて、すぐ実行できて、すぐ効果がでるポイントが沢山書かれていますが、その中からひとつだけご紹介します。
片づけが得意な人と苦手な人とでは、身のまわりが散らかる原因となる「ある動作」について、意識の向け方が大きく異なります。誰もが日常、何気なくやっている「ある動作」とは、いったい何だと思いますか?
ヒントは、ひらがなで2文字です。
答えは「おく」です。もちろん「おく」とは、モノを「置く」という動作のことです。片づけが得意な人は、デスクやテーブル、そしてどんな場所でもモノを置くときに、いつも散らからないよう注意を払っています。反対に、片づけが苦手な人は、「置く」という動作に対していつも無意識です。
(中略)
本書のタイトルは、『たった1分で人生が変わる 片づけの習慣』ですが、彼女とのやりとりを通じて、私は「1分どころではなく、たった0.5秒で人生が変わるのではないか」という気づきを得ました。つまり、片づけが苦手な人は、無頓着な動作である「置く」に意識を向け、行動するだけで、身のまわりが劇的に片づき始め、生活、仕事、そして人生が変わっていくのです。
「たった一分で人生が変わる。片づけの習慣」(小松易著)p16-p17から引用抜粋
ということで、今年は先ずは身のまわりをキチンと片づけて、今年の夢の実現に向かって飛んでいこうと思います(^^)v

今日は久しぶりに「仕事術」についての記事です。
お正月に本屋にブラリと行って、ふと目にとまった本。書名は「たった1分で人生が変わる。片づけの習慣」で、パラパラとめくってすぐにそのまま買いました。
私は片付けが苦手で、すぐに書類が溜まってしまって捜し物をする羽目になることが多いので、「超整理法」(野口悠紀雄著)とか、「掃除道」(鍵山秀三郎著)などの本を読んで、できることはやってきたつもりでした。
それでも昨年の暮れからお正月にかけて、結局デスクの上は片づけられないまま新年を迎えて、つい先日必要に迫られて片づけた位です。そんな私にピッタリの本だと感じました。内容は単なる整理法の羅列ではなく、「片づけ」というものが、そのまま人生の夢の実現にも大きく影響を与えるという観点から書かれていましたので、このブログのテーマ「夢の実現」にそのまま当てはまると思い、皆さんにもご紹介させて頂くことにしました。分かりやすくて、すぐ実行できて、すぐ効果がでるポイントが沢山書かれていますが、その中からひとつだけご紹介します。
片づけが得意な人と苦手な人とでは、身のまわりが散らかる原因となる「ある動作」について、意識の向け方が大きく異なります。誰もが日常、何気なくやっている「ある動作」とは、いったい何だと思いますか?
ヒントは、ひらがなで2文字です。
答えは「おく」です。もちろん「おく」とは、モノを「置く」という動作のことです。片づけが得意な人は、デスクやテーブル、そしてどんな場所でもモノを置くときに、いつも散らからないよう注意を払っています。反対に、片づけが苦手な人は、「置く」という動作に対していつも無意識です。
(中略)
本書のタイトルは、『たった1分で人生が変わる 片づけの習慣』ですが、彼女とのやりとりを通じて、私は「1分どころではなく、たった0.5秒で人生が変わるのではないか」という気づきを得ました。つまり、片づけが苦手な人は、無頓着な動作である「置く」に意識を向け、行動するだけで、身のまわりが劇的に片づき始め、生活、仕事、そして人生が変わっていくのです。
「たった一分で人生が変わる。片づけの習慣」(小松易著)p16-p17から引用抜粋
ということで、今年は先ずは身のまわりをキチンと片づけて、今年の夢の実現に向かって飛んでいこうと思います(^^)v

2012年07月15日
Take it Easy
今回の大雨は本当にすごかったですね。皆さん、被害などなかったでしょうか。被害に遭われたかた、心からお見舞い申し上げます。
今日の言葉は、"Take it Easy"です。
辞書では、
|【1】気分を楽にして、焦らずに気楽にやれ、無理しないでね、あくせくするな
|【2】バイバイ、じゃあね、さようなら◆【用法】別れ際の挨拶として使われる
という意味になっています。
映画タイタニックの最初のシーンで、海底のタイタニックを潜水ロボットを使って探索して、ロボットがドアを通り抜けようとして、ギリギリでひっかかりそうになったとき、ボスがロボットを操作している仲間に、"Take it Easy !"と言います。その日本語字幕が、「注意しろ」となっていて、日本語字幕の大家、戸田奈津子さんの訳ですから、さすがだと思いました。
日本であれば、「慎重に…」「気をつけて…」という表現になるところが、英語では直訳すると、「易しく取り扱いなさい」となるところが、欧米文化らしいと思います。
人間、大舞台に立つとどうしても、肩に力が入って緊張したりして、日頃の実力が出ないもの。 そんなときは、確かに肩の力を抜いて、意識して「易しく取り組む」(Take it Easy)方が、上手く行きそうですね。
やる気スイッチをオンにして、旺盛なチャレンジ精神を持ちつつ、実際の場では、"Take it Easy !"と、自分に言い聞かせてやりたいものです。
と言うところで、今日はこの辺で。
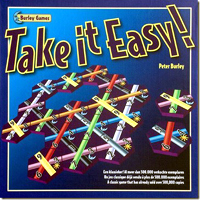
今日の言葉は、"Take it Easy"です。
辞書では、
|【1】気分を楽にして、焦らずに気楽にやれ、無理しないでね、あくせくするな
|【2】バイバイ、じゃあね、さようなら◆【用法】別れ際の挨拶として使われる
という意味になっています。
映画タイタニックの最初のシーンで、海底のタイタニックを潜水ロボットを使って探索して、ロボットがドアを通り抜けようとして、ギリギリでひっかかりそうになったとき、ボスがロボットを操作している仲間に、"Take it Easy !"と言います。その日本語字幕が、「注意しろ」となっていて、日本語字幕の大家、戸田奈津子さんの訳ですから、さすがだと思いました。
日本であれば、「慎重に…」「気をつけて…」という表現になるところが、英語では直訳すると、「易しく取り扱いなさい」となるところが、欧米文化らしいと思います。
人間、大舞台に立つとどうしても、肩に力が入って緊張したりして、日頃の実力が出ないもの。 そんなときは、確かに肩の力を抜いて、意識して「易しく取り組む」(Take it Easy)方が、上手く行きそうですね。
やる気スイッチをオンにして、旺盛なチャレンジ精神を持ちつつ、実際の場では、"Take it Easy !"と、自分に言い聞かせてやりたいものです。
と言うところで、今日はこの辺で。
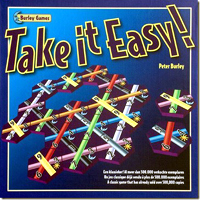
2012年02月08日
カリスマのスピード仕事術 (2)
今日は先週に引き続き、「カリスマのスピード仕事術」のその2です。

小室女史は、(株)資生堂に入社後、社内ビジネスモデル・コンテストで優勝され、育児休業者の職場復帰支援事業を社内ベンチャーとして立ち上げられたそうです。資生堂を退職後、2006年に(株)ワーク・ライフバランスを設立され、育児休業者、うつ病などによる休業者の職場復帰を支援するプログラムを開発され、約200社に導入されたということです。
では、小室女史のインタビューの中から引用させて頂きます。
|小室 まず基本中の基本は、その仕事をできるかぎり小分けにして、少しずつ処
|理できるようにすることですね。イヤな仕事や苦手な仕事って、まとまった時間
|をとっていっぺんに片づけようとしがちですよね。でも、それこそが先送りの最
|大の原因なんですよ。イヤな仕事を長時間続けるのはそうとうな苦痛ですから、
|ついネットサーフィンなんかを始めてしまう。(中略)
|
|小室 そこで私が考えたのが、「イヤな仕事は小分けにして、好きな仕事のあい
|だに細かく挟んで処理していく」というやり方です。(中略)実際にやってみる
|とわかりますが、好きな仕事をしたあとは気持ちに勢いがついているので、嫌い
|な仕事にも取りかかりやすいんです。(中略)
|
|一方、嫌いな仕事をやっている最中も、「あと30分経てば、好きな仕事が待っ
|ている」と思うと、意外と頑張れるもの。要は、好きな仕事が嫌いな仕事をやっ
|た「ご褒美」になるわけです。

まず、「仕事を小分けにする」という手法は良く知られているやり方で、この本の中でも何人もの人が言われていましたが、私の場合、上記のこの小室女史の文章を読んで初めて、よしやってみようという気になりました。その理由は自分ではよく分かりませんが、「まず基本中の基本は…」という表現が、あるインパクトになったことは感じています。
また、引用の後半部分の、「好きな仕事が嫌いな仕事をやった『ご褒美』になる」という表現も分かりやすくて、こちらもまた、実際にやってみようという気になりました。
ある人からあることを、色々と理路整然と説明されたり諭されて、頭では「なるほど」と理解できても、そのことを実際に自分がやるところまでいかないことがあります。一方、分かり切った当たり前のことを別の人から言われて、今度は、スッとそれを実行に移したくなることもあります。
この小室女史の記事を読んだ時の自分が、丁度このような感じでした。実際その後、大きな時間のかかる仕事は小さく分割して、それを毎日少しずつやるようになり、また気乗りがしない仕事も、その後に楽しい仕事を用意することによって、取りかかれるようになりました。
とにかく大切なことは、理論を頭で学ぶことではなく、それを実行に移し、成果を上げることだと思います。
私も、人に色々なことをご指導させて頂くことが多いので、どうやれば相手の人に受け入れられて、そして実行に移してもらえるかを考えながら、自分の仕事に生かしていこうと思いました。
と言うところで、今日はこの辺で。

小室女史は、(株)資生堂に入社後、社内ビジネスモデル・コンテストで優勝され、育児休業者の職場復帰支援事業を社内ベンチャーとして立ち上げられたそうです。資生堂を退職後、2006年に(株)ワーク・ライフバランスを設立され、育児休業者、うつ病などによる休業者の職場復帰を支援するプログラムを開発され、約200社に導入されたということです。
では、小室女史のインタビューの中から引用させて頂きます。
|小室 まず基本中の基本は、その仕事をできるかぎり小分けにして、少しずつ処
|理できるようにすることですね。イヤな仕事や苦手な仕事って、まとまった時間
|をとっていっぺんに片づけようとしがちですよね。でも、それこそが先送りの最
|大の原因なんですよ。イヤな仕事を長時間続けるのはそうとうな苦痛ですから、
|ついネットサーフィンなんかを始めてしまう。(中略)
|
|小室 そこで私が考えたのが、「イヤな仕事は小分けにして、好きな仕事のあい
|だに細かく挟んで処理していく」というやり方です。(中略)実際にやってみる
|とわかりますが、好きな仕事をしたあとは気持ちに勢いがついているので、嫌い
|な仕事にも取りかかりやすいんです。(中略)
|
|一方、嫌いな仕事をやっている最中も、「あと30分経てば、好きな仕事が待っ
|ている」と思うと、意外と頑張れるもの。要は、好きな仕事が嫌いな仕事をやっ
|た「ご褒美」になるわけです。

まず、「仕事を小分けにする」という手法は良く知られているやり方で、この本の中でも何人もの人が言われていましたが、私の場合、上記のこの小室女史の文章を読んで初めて、よしやってみようという気になりました。その理由は自分ではよく分かりませんが、「まず基本中の基本は…」という表現が、あるインパクトになったことは感じています。
また、引用の後半部分の、「好きな仕事が嫌いな仕事をやった『ご褒美』になる」という表現も分かりやすくて、こちらもまた、実際にやってみようという気になりました。
ある人からあることを、色々と理路整然と説明されたり諭されて、頭では「なるほど」と理解できても、そのことを実際に自分がやるところまでいかないことがあります。一方、分かり切った当たり前のことを別の人から言われて、今度は、スッとそれを実行に移したくなることもあります。
この小室女史の記事を読んだ時の自分が、丁度このような感じでした。実際その後、大きな時間のかかる仕事は小さく分割して、それを毎日少しずつやるようになり、また気乗りがしない仕事も、その後に楽しい仕事を用意することによって、取りかかれるようになりました。
とにかく大切なことは、理論を頭で学ぶことではなく、それを実行に移し、成果を上げることだと思います。
私も、人に色々なことをご指導させて頂くことが多いので、どうやれば相手の人に受け入れられて、そして実行に移してもらえるかを考えながら、自分の仕事に生かしていこうと思いました。
と言うところで、今日はこの辺で。