2012年02月29日
絶望の向こうに成功が…
今日も前回に引き続き、ナポレオン・ヒル著の「成功哲学」の本の中からの引用の後半です。
早速、ご紹介します。
|■絶望の向こうに成功が待っている
|
|あとでこの話(ダービー達があきらめた地層からたった3フィート下か
|ら、何百万ドルもの金鉱が掘り出された話)を聴いたダービーは心に深
|く後悔した。しかし、この大失敗の経験は、その後ダービーが生命保険
|のセールスをはじめるようになってから大いに役立ったのである。
|
|西部での大失敗がほんの些細な不注意から生じたことを悟った彼は、新
|しく保険の世界に飛び込むに当たって強く自分自身にこう言い聞かせた。
|「見込客が”ノーと言っても”、決してあきらめたりすまい。鉱山での
|失敗は二度とくりかえさないようにしよう!!」と。
|
|またたくうちにダービーは年間売り上げが100万ドルを越す実績を上
|げ、優秀セールスマン・グループのメンバーに加えられるまでに成功し
|たのである。彼は”すぐあきらめる男”から、”食いついたら離さない
|男”に変身したのだ。
|
|いつの場合でも、成功を勝ちとるまでの人生、それは絶望と挫折のくり
|返しなのだ。一時的な敗北ですべてをあきらめてしまうことはごく簡単
|なことであり、しかも、その挫折にもっともらしい理由をつけることは
|それほどむずかしいことではない。だから、ほとんどの人々が一時的な
|敗北ですぐに願望を棄ててしまうのである。
|
|アメリカで成功者と呼ばれている500人以上もの人々がわたくしに語っ
|たことばを借りるならば、「偉大な成功というものは、人々が敗北に兜
|を脱いだ時点を”ほんの少しだけ過ぎたとき”にやってくる。」ものな
|のだ。失敗とは、ずる賢くて皮肉たっぷりなペテン師のようなものであ
|る。われわれが成功に手がとどきそうになったときに必要なものは、こ
|のペテン師に惑わされない明敏な知識なのである。
|
|(ナポレオン・ヒル 著 「成功哲学」 p.17-18から引用)
このお話を引用しながら、私が中学生の時の、ある出来事を思い出しました。
私が中学3年の卒業前、丁度今頃、体育の授業でサッカーをやっていた時、友達がボールを今まさに蹴ろうとした時、私がそのボールを横からサッと先に蹴りました。それが間一髪だったので、友達は勢いが止まらずそのまま私の足を蹴り上げて、私は当時小柄だったので、フワッと宙に飛び、不自然な体勢で着地したため、右足のスネを骨折してしまいました。
その時、体育の先生が言われたことを今でも覚えています。保健室でギブスに右足を固められて痛みをこらえている私に、「骨を折るくらい、なんでんなか。骨を折ると、そこは治ったあとは前より、もっと強くなるとばい」と。
当時から素直な子供だった私は(自分で言うか)、「そうか。骨を折るとそこは返って強くなるんだ」と強く思いました。そのことが医学的に根拠のあることだったかどうかは分かりませんが、それ以降今日まで、私は身体のどこかを痛めたりすると、「これで返って強くなる(^^)v」と思って生きてきました。
さて、人生には失敗や挫折はつきものですが、挫折はいわば「心のケガ」。となると、心のケガである挫折をすれば、それだけ心も強くなるということになります。
話は戻って、ダービーもゴールド・ラッシュの経験では、骨身に染みる大失敗をして後悔をしたものの、その経験が彼の心をとてつもなく強くし、それからの人生に大きな恵みをもたらしたのだと思います。
それは、ゴールド・ラッシュでの一発勝負で得たかもしれない成功より、その後の人生に於いて生涯役に立つ、はるかに大きな宝物をダービーは得たことになったのだと思います。
私の子供の頃の思い出話も出てきて、長文になってしまいました。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。

早速、ご紹介します。
|■絶望の向こうに成功が待っている
|
|あとでこの話(ダービー達があきらめた地層からたった3フィート下か
|ら、何百万ドルもの金鉱が掘り出された話)を聴いたダービーは心に深
|く後悔した。しかし、この大失敗の経験は、その後ダービーが生命保険
|のセールスをはじめるようになってから大いに役立ったのである。
|
|西部での大失敗がほんの些細な不注意から生じたことを悟った彼は、新
|しく保険の世界に飛び込むに当たって強く自分自身にこう言い聞かせた。
|「見込客が”ノーと言っても”、決してあきらめたりすまい。鉱山での
|失敗は二度とくりかえさないようにしよう!!」と。
|
|またたくうちにダービーは年間売り上げが100万ドルを越す実績を上
|げ、優秀セールスマン・グループのメンバーに加えられるまでに成功し
|たのである。彼は”すぐあきらめる男”から、”食いついたら離さない
|男”に変身したのだ。
|
|いつの場合でも、成功を勝ちとるまでの人生、それは絶望と挫折のくり
|返しなのだ。一時的な敗北ですべてをあきらめてしまうことはごく簡単
|なことであり、しかも、その挫折にもっともらしい理由をつけることは
|それほどむずかしいことではない。だから、ほとんどの人々が一時的な
|敗北ですぐに願望を棄ててしまうのである。
|
|アメリカで成功者と呼ばれている500人以上もの人々がわたくしに語っ
|たことばを借りるならば、「偉大な成功というものは、人々が敗北に兜
|を脱いだ時点を”ほんの少しだけ過ぎたとき”にやってくる。」ものな
|のだ。失敗とは、ずる賢くて皮肉たっぷりなペテン師のようなものであ
|る。われわれが成功に手がとどきそうになったときに必要なものは、こ
|のペテン師に惑わされない明敏な知識なのである。
|
|(ナポレオン・ヒル 著 「成功哲学」 p.17-18から引用)
このお話を引用しながら、私が中学生の時の、ある出来事を思い出しました。
私が中学3年の卒業前、丁度今頃、体育の授業でサッカーをやっていた時、友達がボールを今まさに蹴ろうとした時、私がそのボールを横からサッと先に蹴りました。それが間一髪だったので、友達は勢いが止まらずそのまま私の足を蹴り上げて、私は当時小柄だったので、フワッと宙に飛び、不自然な体勢で着地したため、右足のスネを骨折してしまいました。
その時、体育の先生が言われたことを今でも覚えています。保健室でギブスに右足を固められて痛みをこらえている私に、「骨を折るくらい、なんでんなか。骨を折ると、そこは治ったあとは前より、もっと強くなるとばい」と。
当時から素直な子供だった私は(自分で言うか)、「そうか。骨を折るとそこは返って強くなるんだ」と強く思いました。そのことが医学的に根拠のあることだったかどうかは分かりませんが、それ以降今日まで、私は身体のどこかを痛めたりすると、「これで返って強くなる(^^)v」と思って生きてきました。
さて、人生には失敗や挫折はつきものですが、挫折はいわば「心のケガ」。となると、心のケガである挫折をすれば、それだけ心も強くなるということになります。
話は戻って、ダービーもゴールド・ラッシュの経験では、骨身に染みる大失敗をして後悔をしたものの、その経験が彼の心をとてつもなく強くし、それからの人生に大きな恵みをもたらしたのだと思います。
それは、ゴールド・ラッシュでの一発勝負で得たかもしれない成功より、その後の人生に於いて生涯役に立つ、はるかに大きな宝物をダービーは得たことになったのだと思います。
私の子供の頃の思い出話も出てきて、長文になってしまいました。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。

2012年02月26日
早すぎる”あきらめ”
前回のブログで、"Never Give Up"の大切さのお話をさせて頂きましたが、このことに関連して、これもずいぶん昔に読んだ本のエピソードを思い出しましたので、今日はそれをご紹介させて頂きます。
今日の引用は、ナポレオン・ヒル著の「成功哲学」の本の中からです。私が持っているこの本の発行年月は、1981年の4月で第19版となっていましたので、30年ほど前に買ったようです。その後何度も読み直したとは言え、30年も前に読んだ本の一節を、ふと思い出すのですから、やはり読書というものは、自分の人生の生き方・考え方に大きな影響を与えるものだと、あらためて思いました。
前置きが長くなりました。では引用です。
|早すぎる”あきらめ”
|
|失敗の最大の原因は、一時的な敗北にあまりにも簡単に”あきらめ”て
|しまうことである。これは誰もが一度や二度は経験があるのではないだ
|ろうか?
|
|ゴールドラッシュの時代に、R・U・ダービーの叔父もその”熱に浮かさ
|れて”西部へ出かけていった。だが、叔父は”金塊よりも大切なものが、
|実は人間の中にあるのだ”という知識に欠けていたため、大失敗をする
|のである。
|
|叔父はシャベルとピックをもって西部にやってきた。そして間もなく
|鉱脈を掘り当てたのである。(中略)ドリルを掘り進むほどにダービー
|達の夢は大きくふくらんでいった。しかし、ある日突然、金の鉱脈が
|消えたのである。彼らの夢ははかなくもくずれ去った。もうそこには
|ひとかけらの金も残されてはいなかったのである。それでもダービー
|達は絶望と闘いながら、祈るような気持ちでさらにドリルを掘り下げ
|ていった。しかし結局、彼らはすべてが水の泡と消えてしまった現実
|を認めざるを得なかった。彼らは”最期の決断を下し”採掘設備のす
|べてをわずか数百ドルの捨て値でクズ屋に売り払い、故郷へ帰ったの
|である。
|
|ところが、設備を買い取ったそのクズ屋は、念のために鉱山技師に頼ん
|で本当にこの鉱山がダメなものかどうかを調査したのである。(中略)
|その結果、調査に当たった技師の計算にまちがいがなければ、金鉱脈は
|ダービー達があきらめた地層から「たった3フィート下に」現れるはず
|であった。そうして事実、その地層から金鉱脈は再発見されたのである。
|クズ屋はこの鉱脈から何百万ドルもの金鉱を掘り出したのである。
|
|(ナポレオン・ヒル 著 「成功哲学」 p.16-17から引用)
今日は、あらためて私がコメントする必要もないくらい、印象的なお話ですね。しかもこれは実際にあったお話ですから、説得力も大きいと思います。
引用が長くなりましたので、この後半については、次回またご紹介させて頂きます。
ともかく、「もうひと頑張り」が、いかに大切かということに尽きるようですね。
今日はこの辺で。

今日の引用は、ナポレオン・ヒル著の「成功哲学」の本の中からです。私が持っているこの本の発行年月は、1981年の4月で第19版となっていましたので、30年ほど前に買ったようです。その後何度も読み直したとは言え、30年も前に読んだ本の一節を、ふと思い出すのですから、やはり読書というものは、自分の人生の生き方・考え方に大きな影響を与えるものだと、あらためて思いました。
前置きが長くなりました。では引用です。
|早すぎる”あきらめ”
|
|失敗の最大の原因は、一時的な敗北にあまりにも簡単に”あきらめ”て
|しまうことである。これは誰もが一度や二度は経験があるのではないだ
|ろうか?
|
|ゴールドラッシュの時代に、R・U・ダービーの叔父もその”熱に浮かさ
|れて”西部へ出かけていった。だが、叔父は”金塊よりも大切なものが、
|実は人間の中にあるのだ”という知識に欠けていたため、大失敗をする
|のである。
|
|叔父はシャベルとピックをもって西部にやってきた。そして間もなく
|鉱脈を掘り当てたのである。(中略)ドリルを掘り進むほどにダービー
|達の夢は大きくふくらんでいった。しかし、ある日突然、金の鉱脈が
|消えたのである。彼らの夢ははかなくもくずれ去った。もうそこには
|ひとかけらの金も残されてはいなかったのである。それでもダービー
|達は絶望と闘いながら、祈るような気持ちでさらにドリルを掘り下げ
|ていった。しかし結局、彼らはすべてが水の泡と消えてしまった現実
|を認めざるを得なかった。彼らは”最期の決断を下し”採掘設備のす
|べてをわずか数百ドルの捨て値でクズ屋に売り払い、故郷へ帰ったの
|である。
|
|ところが、設備を買い取ったそのクズ屋は、念のために鉱山技師に頼ん
|で本当にこの鉱山がダメなものかどうかを調査したのである。(中略)
|その結果、調査に当たった技師の計算にまちがいがなければ、金鉱脈は
|ダービー達があきらめた地層から「たった3フィート下に」現れるはず
|であった。そうして事実、その地層から金鉱脈は再発見されたのである。
|クズ屋はこの鉱脈から何百万ドルもの金鉱を掘り出したのである。
|
|(ナポレオン・ヒル 著 「成功哲学」 p.16-17から引用)
今日は、あらためて私がコメントする必要もないくらい、印象的なお話ですね。しかもこれは実際にあったお話ですから、説得力も大きいと思います。
引用が長くなりましたので、この後半については、次回またご紹介させて頂きます。
ともかく、「もうひと頑張り」が、いかに大切かということに尽きるようですね。
今日はこの辺で。

2012年02月22日
これが成功する人の条件です
今日も「集中力」の本からのご紹介です。
|これが成功する人の条件です
|
|重大な時期に選ばれるのはたいてい、天才ではありません。才能は他の人
|と変わらないけれど、たゆまず集中して努力してこそ成果が生まれると知
|っている人です。ビジネスにおいて「奇跡」はたまたま「起こる」もので
|はないと知っている人です。
|
|そう言う人は、奇跡を起こす方法は、一つの計画をあきらめず、最後まで
|やりとおすことだと知っています。成功する人と失敗する人のちがいは、
|それだけです。成功する人はものごとの完成を予感する習慣を持ち、つね
|に成功を確信しています。失敗する人はものごとの挫折を想像する習慣を
|もち、そう予測し、実際に失敗を引き寄せます。
|
|(セロン・Q・デュモン 著 「集中力」 レッスン1 p.22から引用)
以前このブログで、自己啓発書に於いて、夢を実現させるために必要なこととして強調していることには、共通していることが多いとお話しましたが、今日の引用部分にもそれが登場しています。
それは、「あきらめず、最後までやりとおすこと」ということです。
「失敗」や「敗北」と言われる出来事も、それをそこで止めてしまうからそうなるのであり、本人が「これは失敗ではなく、成功への通過点だ」と考え続ける限り、少なくとも本人の中では失敗ではありません。
かの松下幸之助氏も、著書の中でこう言われていました。「私は数限りない失敗をしてきました。しかし、私はそれでも止めずに、成功するまでやり続けてきたので、今日があると思います」と。
ポイントはやはり、”Never Give Up!” のようですね。
今日はこの辺で。
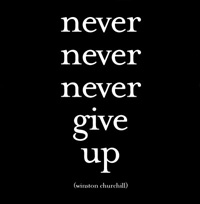
|これが成功する人の条件です
|
|重大な時期に選ばれるのはたいてい、天才ではありません。才能は他の人
|と変わらないけれど、たゆまず集中して努力してこそ成果が生まれると知
|っている人です。ビジネスにおいて「奇跡」はたまたま「起こる」もので
|はないと知っている人です。
|
|そう言う人は、奇跡を起こす方法は、一つの計画をあきらめず、最後まで
|やりとおすことだと知っています。成功する人と失敗する人のちがいは、
|それだけです。成功する人はものごとの完成を予感する習慣を持ち、つね
|に成功を確信しています。失敗する人はものごとの挫折を想像する習慣を
|もち、そう予測し、実際に失敗を引き寄せます。
|
|(セロン・Q・デュモン 著 「集中力」 レッスン1 p.22から引用)
以前このブログで、自己啓発書に於いて、夢を実現させるために必要なこととして強調していることには、共通していることが多いとお話しましたが、今日の引用部分にもそれが登場しています。
それは、「あきらめず、最後までやりとおすこと」ということです。
「失敗」や「敗北」と言われる出来事も、それをそこで止めてしまうからそうなるのであり、本人が「これは失敗ではなく、成功への通過点だ」と考え続ける限り、少なくとも本人の中では失敗ではありません。
かの松下幸之助氏も、著書の中でこう言われていました。「私は数限りない失敗をしてきました。しかし、私はそれでも止めずに、成功するまでやり続けてきたので、今日があると思います」と。
ポイントはやはり、”Never Give Up!” のようですね。
今日はこの辺で。
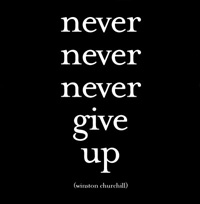
2012年02月19日
「集中すること」を習慣に
今日も、「集中力」の本からのご紹介です。今日は具体的な「集中力」を高める方法について言及されています。
|毎日、十分ほどでかまいません。「集中すること」を習慣にしてください。
|
|何か一つの考えを選び、どれくらいの時間そのことを考えつづけられるか、試し
|てみてください。最初のうちは時計をそばに置き、時間を計るのがいいでしょう。
|たとえば健康について考えようと決めると、それによって集中力を伸ばせるだけ
|でなく、考えた内容から多くのものを得ることができます。
|
|「健康はこの世で最高の宝物である」と考えてください。それ以外の考えは頭の
|なかに入りこまないように、浮かんできたらすぐに追い出してください。(中略)
|現在の状況に関係なく、あなたは「自分がこうなりたいと思う人間」になってい
|ると考え、それ以外の考えには目をつむりましょう。
|
|たとえば持病のある人なら、最初は病気のことを忘れようとしても難しいでしょ
|うが、まもなくそういったネガティブな考えを閉め出して、なりたい姿になって
|いる自分を思い描くことができます。こうして集中するたびに健康の完璧なイメー
|ジが形づくられ、やがてそれが現実のものになって、あなたは丈夫で健康な人に
|なります。
|
|(セロン・Q・デュモン 著 「集中力」 レッスン1 p.166-167から引用)
ここでは「健康」ということを題材に、集中する方法について述べられていますが、この「健康」という言葉を、自分の夢や目標に置き換えて試してみることができます。
この本には、集中力を高めるための具体的なエクササイズが、19個紹介されています。私がこの本を買ったのは5年前で、その後4回読み返して、昨年の秋、またふと思い出して5回に入りました。そして今回初めて、紹介されていたエクササイズを実際にやってみました。
エクササイズを実際にやってみて分かったことは、本を読むことは大切で有益なことですが、もっと大切なことは、そこで学んだことを実際に実行してみることだということでした。
私は筋トレとストレッチを毎日やっていますが、これもただ、「私は筋力がついて、しなやかな身体をもっている」とイメージするだけでは、その目標はいつまで経っても実現しません。イメージしながら、毎日地味で、きつい筋トレとストレッチを継続していくことによってはじめて、少しずつ身体が変わっていきます。
大切なことは、まず夢を持つこと、その実現した姿を集中してイメージすること。そしてイメージと共に具体的な行動を継続していくこと。その結果、いつの日かその夢が実現している自分に気がつく、ということだと思います。
長くなりましたので、今日はこの辺で。

|毎日、十分ほどでかまいません。「集中すること」を習慣にしてください。
|
|何か一つの考えを選び、どれくらいの時間そのことを考えつづけられるか、試し
|てみてください。最初のうちは時計をそばに置き、時間を計るのがいいでしょう。
|たとえば健康について考えようと決めると、それによって集中力を伸ばせるだけ
|でなく、考えた内容から多くのものを得ることができます。
|
|「健康はこの世で最高の宝物である」と考えてください。それ以外の考えは頭の
|なかに入りこまないように、浮かんできたらすぐに追い出してください。(中略)
|現在の状況に関係なく、あなたは「自分がこうなりたいと思う人間」になってい
|ると考え、それ以外の考えには目をつむりましょう。
|
|たとえば持病のある人なら、最初は病気のことを忘れようとしても難しいでしょ
|うが、まもなくそういったネガティブな考えを閉め出して、なりたい姿になって
|いる自分を思い描くことができます。こうして集中するたびに健康の完璧なイメー
|ジが形づくられ、やがてそれが現実のものになって、あなたは丈夫で健康な人に
|なります。
|
|(セロン・Q・デュモン 著 「集中力」 レッスン1 p.166-167から引用)
ここでは「健康」ということを題材に、集中する方法について述べられていますが、この「健康」という言葉を、自分の夢や目標に置き換えて試してみることができます。
この本には、集中力を高めるための具体的なエクササイズが、19個紹介されています。私がこの本を買ったのは5年前で、その後4回読み返して、昨年の秋、またふと思い出して5回に入りました。そして今回初めて、紹介されていたエクササイズを実際にやってみました。
エクササイズを実際にやってみて分かったことは、本を読むことは大切で有益なことですが、もっと大切なことは、そこで学んだことを実際に実行してみることだということでした。
私は筋トレとストレッチを毎日やっていますが、これもただ、「私は筋力がついて、しなやかな身体をもっている」とイメージするだけでは、その目標はいつまで経っても実現しません。イメージしながら、毎日地味で、きつい筋トレとストレッチを継続していくことによってはじめて、少しずつ身体が変わっていきます。
大切なことは、まず夢を持つこと、その実現した姿を集中してイメージすること。そしてイメージと共に具体的な行動を継続していくこと。その結果、いつの日かその夢が実現している自分に気がつく、ということだと思います。
長くなりましたので、今日はこの辺で。

2012年02月16日
人を泉に連れていくことはできるが…
今日の言葉も、前回に引き続き「集中力」の本からのご紹介です。
早速、引用させて頂きます。
|「人を泉に連れていくことはできるが 水を飲ませることはできない」
|
|良い本を読んでも、たいして得るものがなかったと言う人が大勢います。そうい
|う人たちは、どんな本も講座も、できるのは自分の可能性に目覚めさせることだ
|けだと気づいていません。意志のパワーを使うように刺激するのが本の役目です。
|誰かにこの世の終わりまでものを教えつづけたとしても、その人が身につけるの
|は自分自身で学んだことだけです。ことわざどおり、「人を泉に連れていくこと
|はできるが、水を飲ませることはできない」のです。(中略)
|
|ほとんどのことは可能です。過酷な課題であるかもしれませんが、課せられたこ
|とが過酷であるほど、報いも大きいのです。私たちを育ててくれるのは、困難な
|ことです。少し努力すればできること、ほとんど能力を必要としないことは、達
|成できることもほんのわずかです。ですから困難な課題にひるんではいけません。
|困難な課題を一つやり遂げて手にするものは、楽な課題で1ダースの成功をおさ
|めたときよりもずっと大きいのです。
|
|(セロン・Q・デュモン 著 「集中力」 レッスン1 p.18-20から引用)
引用前半の、「人を泉に連れていくことはできても、水を飲ませることはできない」は有名なことわざですので、ご存じの方が多いと思いますが、これを自分のこととして考えたことは意外と少ないのではないでしょうか。
大切なことは、「(自分の)意志のパワーを使う」という点だと思います。前回ご紹介した、「人は誰でも二人の自分をもっている」にあったように、人の心には前進しようとする自分と、後退しようとする自分があって、前進しようとする自分が、「よし!泉の水を飲んで元気を出して頑張るぞ!」と思って泉のほとりまで行っても、そこで後退しようとする自分が、「いや、この泉の水を飲んだってきっと美味しくないから、やめとこ」と言ってしまったら、そこで終わりです。
引用後半では、「困難な課題を一つやり遂げて手にするものは、楽な課題で1ダースの成功をおさめたときよりもずっと大きい」というところが、ポイントだと思います。
人生では、自分で望まなくても、試練ともいうべき困難が降りかかってくることがありますが、その時、その困難が大きければ大きいほど、「このことが自分を成長させてくれるのだ」と思い、そう言い聞かせることができれば、その困難は本当に自分に大きな恵みをもたらしてくれると思います。
口でいうほど簡単なことではありませんが、そういう時こそ、自分の尊い「意志のパワー」を発揮させて、乗り切っていきたいものだと思います。
今日はこの辺で。

早速、引用させて頂きます。
|「人を泉に連れていくことはできるが 水を飲ませることはできない」
|
|良い本を読んでも、たいして得るものがなかったと言う人が大勢います。そうい
|う人たちは、どんな本も講座も、できるのは自分の可能性に目覚めさせることだ
|けだと気づいていません。意志のパワーを使うように刺激するのが本の役目です。
|誰かにこの世の終わりまでものを教えつづけたとしても、その人が身につけるの
|は自分自身で学んだことだけです。ことわざどおり、「人を泉に連れていくこと
|はできるが、水を飲ませることはできない」のです。(中略)
|
|ほとんどのことは可能です。過酷な課題であるかもしれませんが、課せられたこ
|とが過酷であるほど、報いも大きいのです。私たちを育ててくれるのは、困難な
|ことです。少し努力すればできること、ほとんど能力を必要としないことは、達
|成できることもほんのわずかです。ですから困難な課題にひるんではいけません。
|困難な課題を一つやり遂げて手にするものは、楽な課題で1ダースの成功をおさ
|めたときよりもずっと大きいのです。
|
|(セロン・Q・デュモン 著 「集中力」 レッスン1 p.18-20から引用)
引用前半の、「人を泉に連れていくことはできても、水を飲ませることはできない」は有名なことわざですので、ご存じの方が多いと思いますが、これを自分のこととして考えたことは意外と少ないのではないでしょうか。
大切なことは、「(自分の)意志のパワーを使う」という点だと思います。前回ご紹介した、「人は誰でも二人の自分をもっている」にあったように、人の心には前進しようとする自分と、後退しようとする自分があって、前進しようとする自分が、「よし!泉の水を飲んで元気を出して頑張るぞ!」と思って泉のほとりまで行っても、そこで後退しようとする自分が、「いや、この泉の水を飲んだってきっと美味しくないから、やめとこ」と言ってしまったら、そこで終わりです。
引用後半では、「困難な課題を一つやり遂げて手にするものは、楽な課題で1ダースの成功をおさめたときよりもずっと大きい」というところが、ポイントだと思います。
人生では、自分で望まなくても、試練ともいうべき困難が降りかかってくることがありますが、その時、その困難が大きければ大きいほど、「このことが自分を成長させてくれるのだ」と思い、そう言い聞かせることができれば、その困難は本当に自分に大きな恵みをもたらしてくれると思います。
口でいうほど簡単なことではありませんが、そういう時こそ、自分の尊い「意志のパワー」を発揮させて、乗り切っていきたいものだと思います。
今日はこの辺で。





