2014年04月27日
オール・アット・ワンス/ホイットニー・ヒューストン
皆さん、こんにちは。
今週は、映画「ゲーテの恋~君に捧ぐ「若きウェルテルの悩み」~」のDVDのことについて書く予定だったのですが、時間の関係でまだ見終えなかったので、代わりに私のお気に入りの音楽のご紹介をさせて頂くことにしました。
世界的なR&Bシンガーであるホイットニー・ヒューストンが、2012年2月11日に、48歳の若さで急逝したというニュースには世界中が驚きましたが、そのことについて、ウィキペディアに下記のように記されています。
ホイットニー・ヒューストン 突然の死
2012年2月11日に、カリフォルニア州ビバリーヒルズにあるビバリーヒルトン・ホテル(英語版)4階客室の
浴槽の中に倒れていたところを発見され、救急隊が20分間にわたって蘇生処置を施したが、同日午後3時
55分(現地時間)に死亡が確認された。48歳没。ホイットニーは、グラミー賞の授賞式を翌日に控え、クライ
ヴ・デイヴィスが主催する恒例の前夜パーティに参加するために、同ホテルに滞在していた。
2012年3月22日、ロサンゼルス郡検視局は会見を開き、死因は不慮の溺死であり、遺体からコカインが
検出されていることから、入浴中にコカインの影響で心臓発作が起こったため、浴槽に沈んだ可能性が高い
という検視結果を発表した。
原因は何にしろ、あのホイットニーの歌声が聞けなくなったことは、本当に残念に思います。ホイットニーのヒット曲はたくさんありますが、その中から『オール・アット・ワンス』をご紹介します。オール・アット・ワンス(All At Once)は、 全米アルバムチャートで14週No.1に輝いたデビュー・スタジオアルバム、Whitney Houston(ホイットニー・ヒューストン)からの4曲目のシングル曲です。
You Tubeチューブで捜してみましたら色々と見つかりましたが、日本語訳もついたものがありましたので、それを紹介させて頂きます。
人生には、心傷つく思い出や経験がつきものですが、この様な歌を通してそのことを見つめると、実はそのことも人生の貴重な大切な思い出であったことが分かるような気がしました。
時間があるときにでも、良かったらどうぞ。
では-
オール・アット・ワンス/ホイットニー・ヒューストン 和訳付き
https://www.youtube.com/watch?v=gmBXJoHeKjs&feature=player_embedded

2014年04月20日
いきいきと生きよ ゲーテに学ぶ
皆さん、こんにちは。
今日も先週に引き続き、ゲーテの言葉のご紹介です。
では、早速。
生きているあいだは、いきいきとしていなさい。 (『ファウスト』)
昼のあいだは、はたらきなさい。 (ボアスレーあての手紙)
二つのことばは、別々に発せられたものだが、もしゲーテの人生観と生き方を、いちばん手短に言い
表しているものを選ぶとしたら、この二つにまさるものはあるまい。ゲーテのような生きることの天才
でなければ、とてもこうは言えない。ときどきこういういぶきを浴びるのはわれわれの薬になる。(中略)
ゲーテが、73歳という齢で恋をしたほどの気の若い人であったのも、やはり同じところから来ていよう。
生きているから、いきいきとせずにはいられず、好きな人に会えば恋をせずにはいられなかったのだろう。
恋をするまでにならなくとも、いつも若々しいのはいいことである。(中略)
昼のあいだ、つまり、夜にならないうちは、はたらきなさい、ということも、ゲーテ自身が実践したことは
言うまでもない。そうでなければ、130巻もの全集の仕事ができるはずはない。
(「いきいきと生きよ ゲーテに学ぶ」著:手塚富雄 p.28-30から抜粋引用)
解説者の手塚富雄氏が、この本のタイトルを「いきいきと生きよ ゲーテに学ぶ」としたのは、このくだりからだったことがうかがわれます。
ゲーテと聞くと、歴史に残る文豪、そして哲学者というイメージがあって、少々近寄りがたい偉人のような感じが強いですが、この本を読んでいくと、ふつうの当たり前のことを述べている、極めて人間らしい人物であることが分かります。
今回このブログを書くにあたって、ウェブでゲーテのことを調べていたところ、数年前に、「ゲーテの恋~君に捧ぐ「若きウェルテルの悩み」~」という映画が公開されたことを知り、興味を持ち、アマゾンで取り寄せることにしました。
来週は、この映画の感想をブログに書きたいと思っています。
と言うところで、今日はこの辺で。

2014年04月13日
いきいきと生きよ ゲーテ
皆さん、こんにちは。
今日はゲーテの言葉をご紹介させて頂きます。
先日古い本箱で、私が大学時代に買って読んだ本が目に止まりました。本の題名は「いきいきと生きよ ゲーテに学ぶ」で、著者は手塚富雄氏です。内容は、著者がゲーテの諸作品の中から色々な言葉を選び出して、それに解説をしているものです。
私が大学生の時に読んだ本ですから、紙面もかなり黄色くなって乾燥していました。その本をパラパラとめくっていたところ、黄色のマーカーがひいてある箇所が目に止まりました。それは、下記の部分です。
「なぜわたしは移ろいやすいのでしょう、ゼウスさま」と、美がたずねた。
「わたしは移ろいやすいものだけを、美しくつくったのだよ」と、神は答えた。 (ゲーテ : 詩「四季」)
ゲーテのこのことばに含まれている意味は、非常に深く、汲みつくせないものをもっている。個人的に考えても、「死」は何人にもまぬかれがたい定めであるが、その死の定めは、実は現在生きていることと、まったく一体のものであることに気がついてくる。(中略)
われわれ人間にできる最善のことは、瞬間を永遠なるものに転化することである。スポーツマンが全力を出し切ってシュートに成功した瞬間に、かれは永遠ということに触れたのである。もっと息の長い事業にしても、大きい時間の流れから見れば瞬間にほかならない。いまの力を出しきって生きること、それがわれわれのできるすべてである。 そういうことを言ったゲーテの別のことばを次にあげておこう。
事物のはかなさについて大騒ぎをし、現世のむなしさの考察にふけっている人々を、
わたしは気の毒に思う。わたしたちがこの世に存在するのは、実際、はかないものを
永遠なものにするためではないか。(「箴言と省察」)
(「いきいきと生きよ ゲーテに学ぶ」著:手塚富雄 p.94-96から抜粋引用)
私がこの本を読んだ学生時代、このゲーテの言葉にマーカーを引いた自分が、何を感じていたのか今となっては思い出せませんが、あれから数十年の歳月がながれ、いままたこの本を読み返して、はじめてゲーテの言葉の真の意味を少しだけ理解できたような気がします。
「わたしたちがこの世に存在するのは、実際、はかないものを永遠なものにするため」というゲーテの言葉をかみしめて、これからの毎日を大切に生きていきたいと思います。
今日はこの辺で。
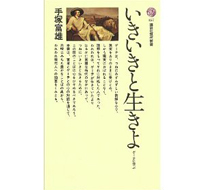
2014年04月06日
選択理論心理学
今日は久しぶりに、このブログのメインテーマらしい話題で、大分以前に読んだ本の、ある箇所を最近ふと思い出しましたので、ご紹介させて頂きます。
「選択理論心理学」。これはアメリカの精神科医ウイリアム・グラッサー博士が提唱している理論ということで、概要は下記のとおりです。少々長いですので、お時間のある時にでもどうぞ。
「選択理論心理学」の三つの原則
原則1
人は、自分自身の行動に対して責任がある。
社会や遺伝や過去の出来事のせいではない。すべては、その人の選択である。
原則2
人は変わることができる。
そして、より効果的な人生を送ることができる。
原則3
人の行動には目的がある。ちょうど、陶芸家が粘土をこねるように、自分の環境を
操作して、自分の欲している心のイメージ写真に近づける行動をする。
以上を説明するのにウイリアム・グラッサー博士はこんな例を挙げています。
「電話が鳴ると受話器をとる。なぜとるのかと聞くと、ベルが鳴ったからだという。みんな外側の刺激(ベルが鳴る)に反応し受話器をとると信じている。これは今まで心理学でいわれてきた刺激・反応理論による行動の説明である。しかし、選択理論心理学ではそう考えない。ベルが鳴ったからというのは無関係ではないが、その人がとりたかったからとったのであり、とることをその人が選択したからとったのである。われわれはそのときどきに、もっとも自分を満足させる行動をとると選択理論心理学では考えるのである。実際、あなたはベルが鳴っても、受話器をとらないときもあるのではないだろうか」(『人生はセルフコントロール』より)
つまり、どんな行動も、自分がそうなりたいから、そうしたいから、そういう行動を選びとっているのです。すなわち、すべての行動は自分が選択したものだということです。自分にとって情けない行動ですら、それは自分がそうしたかったから、それが最善の方法だから選びとったのだということです。
(以上、「絶対営業力」青木仁志氏著/産能大学出版部刊より抜粋)
何となく、逆説的な理論の様な印象もありますが、私が一番大切だと感じたのは、最初に引用した部分の、
原則2
人は変わることができる。
そして、より効果的な人生を送ることができる。
という箇所です。私もこのことをしっかりと理解して、常に自分の望む人生を選択し、日々実践していきたいと思います。
今日はこの辺で。




