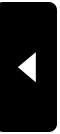2011年10月16日
困った人たち(その2)
今日は先週の続き、「困った人たち」の後半です。
|こうはなりたくないな、と思うタイプがある。あなたのダ ンス教室にも、
|必ずひとりくらいいるのではないだろうか。こういう人、困るのよね、
|というタイプ。
|
|ダンスのマナーにも通じるものがあるので、5タイプに絞って挙げてみ
|たい。よくよく考えてみると、どれも結局は、ふたりで踊ることを知ら
|ない人たちである。(中略)
|
|三つ目は、シャドー人間タイプ。男性に多い。うまく見える。きちんと
|踊っている。シャドーで踊る(ひとりで上体のポジションをつくっての
|練習)のが大好きである。この手の男性には、シャドーで事足りてしまっ
|て相手を道具か何かだと思っている人がいる。腕の中にポンと収まって
|くれる女性がいさえすればよい。このタイプの人と踊ってみると、幽霊
|と踊っている感じがする。パートナーは本人の引き立て役にすぎず、本
|当は私なんかいてもいなくてもいいのね、と言いたくなる。
|
|四つ目は、頼り切りタイプ。こちらは女性に多い。私はだめなのです、
|お任せします、と何から何まで相手に頼りっぱなし。男性のリードを待
|つのは大切だが、それぞれが自立していないと、ふたりのダンスは成立
|しない。シャドー人間と両極端をなす。
|
|(浅野素女 著「踊りませんか?」第4章 p.94-96から引用)
もうひとタイプ残っているのですが、長くなりましたので、五番目とまとめは来週書かせて頂きます。
「困った人たち」を読んでいると、私が以前、「リードとフォロー ダンスの究極」シリーズで書かせて頂いたことの、反対のことが書かれていることに気づかれると思います。
社交ダンスは二人で踊るもので、そこがソロダンスと決定的に異なる点です。ですから、ダンスそのものが、二人のコミュニケーションそのものと言って良いでしょう。
ですから、社交ダンスを学んでいくことが、そのまま日常の対人コミュニケーションに生かされることにもなるのです。
というところで、今日はこの辺で。

|こうはなりたくないな、と思うタイプがある。あなたのダ ンス教室にも、
|必ずひとりくらいいるのではないだろうか。こういう人、困るのよね、
|というタイプ。
|
|ダンスのマナーにも通じるものがあるので、5タイプに絞って挙げてみ
|たい。よくよく考えてみると、どれも結局は、ふたりで踊ることを知ら
|ない人たちである。(中略)
|
|三つ目は、シャドー人間タイプ。男性に多い。うまく見える。きちんと
|踊っている。シャドーで踊る(ひとりで上体のポジションをつくっての
|練習)のが大好きである。この手の男性には、シャドーで事足りてしまっ
|て相手を道具か何かだと思っている人がいる。腕の中にポンと収まって
|くれる女性がいさえすればよい。このタイプの人と踊ってみると、幽霊
|と踊っている感じがする。パートナーは本人の引き立て役にすぎず、本
|当は私なんかいてもいなくてもいいのね、と言いたくなる。
|
|四つ目は、頼り切りタイプ。こちらは女性に多い。私はだめなのです、
|お任せします、と何から何まで相手に頼りっぱなし。男性のリードを待
|つのは大切だが、それぞれが自立していないと、ふたりのダンスは成立
|しない。シャドー人間と両極端をなす。
|
|(浅野素女 著「踊りませんか?」第4章 p.94-96から引用)
もうひとタイプ残っているのですが、長くなりましたので、五番目とまとめは来週書かせて頂きます。
「困った人たち」を読んでいると、私が以前、「リードとフォロー ダンスの究極」シリーズで書かせて頂いたことの、反対のことが書かれていることに気づかれると思います。
社交ダンスは二人で踊るもので、そこがソロダンスと決定的に異なる点です。ですから、ダンスそのものが、二人のコミュニケーションそのものと言って良いでしょう。
ですから、社交ダンスを学んでいくことが、そのまま日常の対人コミュニケーションに生かされることにもなるのです。
というところで、今日はこの辺で。

2011年10月14日
ぬくもりのへや
今日は、最近私の方で作成を手伝わせて頂いたホームページを紹介させて頂きます。
名前は「ぬくもりのへや 自殺防止メーリングリスト」というものです。
urlは下記のとおりです。
「ぬくもりのへや 自殺防止メーリングリスト」
http://nukumorinoheya.pya.jp/
「いのちの電話」というのを聞かれたことがありますか?これは、自殺の一歩手前まで追いつめられた人が、最後に何か話しておきたいというような時に、電話で聞いてあげて、それで思いとどまってもらうことをねらいとしたものです。もう数十年前からあります。
そのスタッフを長くされたかたが、今回インターネットを通じて、同じようなことをしてみたいと立ち上げられたもので、私はブログを通じて知り合った方から紹介を頂き、ホームページの作成を手伝わせて頂きました。
ホームページの中に、「ぬくもりのへやスタッフブログ」というページがあり、そこに次のような記事が載っています。
|山奥の村で生まれて・・! korobokkuru - 2011/10/11(Tue) 23:53
|都会から、初めてこの村を訪れる人の多くが、山中を走り続けるうち
|に、この先に、本当に家があるのだろうかと、そんな不安にかられる
|という。そんな田舎の、村社会の中で、目の悪い子供を持った両親
|は、どんなにか苦しい思いや、辛い思いをしただろうか。近代のよ
|うに、障害者への理解も、まだまだであり、障害者は、座敷牢に入れ
|て、存在を隠されていた、そんな時代から、まだ、あまり遠くないこ
|ろのことですから・・。障害の内容や、その方の受け止め方によっ
|て違うとは思いますが、私が思うには、自分が障害者であることの苦
|しみよりも、自分の子供が障害者であることの方が、はるかに辛いの
|ではなかろうかと思うのです。「ぬくもりのへや」を、どういう者
|が立ち上げたのか、知っていただいた方が、少しでも安心して参加し
|ていただけるのではなかろうかと思って、自分史を、少しづつ書かせ
|ていただきます。
私もできるだけお手伝いさせて頂きたいと思っています。お時間のある時に、良かったらどうぞ。

名前は「ぬくもりのへや 自殺防止メーリングリスト」というものです。
urlは下記のとおりです。
「ぬくもりのへや 自殺防止メーリングリスト」
http://nukumorinoheya.pya.jp/
「いのちの電話」というのを聞かれたことがありますか?これは、自殺の一歩手前まで追いつめられた人が、最後に何か話しておきたいというような時に、電話で聞いてあげて、それで思いとどまってもらうことをねらいとしたものです。もう数十年前からあります。
そのスタッフを長くされたかたが、今回インターネットを通じて、同じようなことをしてみたいと立ち上げられたもので、私はブログを通じて知り合った方から紹介を頂き、ホームページの作成を手伝わせて頂きました。
ホームページの中に、「ぬくもりのへやスタッフブログ」というページがあり、そこに次のような記事が載っています。
|山奥の村で生まれて・・! korobokkuru - 2011/10/11(Tue) 23:53
|都会から、初めてこの村を訪れる人の多くが、山中を走り続けるうち
|に、この先に、本当に家があるのだろうかと、そんな不安にかられる
|という。そんな田舎の、村社会の中で、目の悪い子供を持った両親
|は、どんなにか苦しい思いや、辛い思いをしただろうか。近代のよ
|うに、障害者への理解も、まだまだであり、障害者は、座敷牢に入れ
|て、存在を隠されていた、そんな時代から、まだ、あまり遠くないこ
|ろのことですから・・。障害の内容や、その方の受け止め方によっ
|て違うとは思いますが、私が思うには、自分が障害者であることの苦
|しみよりも、自分の子供が障害者であることの方が、はるかに辛いの
|ではなかろうかと思うのです。「ぬくもりのへや」を、どういう者
|が立ち上げたのか、知っていただいた方が、少しでも安心して参加し
|ていただけるのではなかろうかと思って、自分史を、少しづつ書かせ
|ていただきます。
私もできるだけお手伝いさせて頂きたいと思っています。お時間のある時に、良かったらどうぞ。

2011年10月12日
ヒップアップのコツ
ヒップアップというのは、ダンスをされている人だけでなく、女性なら誰でもあこがれるのではないでしょうか。今日はそのヒップアップのコツを、少しご紹介させて頂きます。
 社交ダンスでは特にラテンダンス(ルンバ・チャチャチャ・サンバなど)を踊る女性(男性もですが)のヒップムーブメントがとても素敵なので、そのヒップアクションを真似したくなりますが、見よう見まねでやると、少々おかしなことになってしまいます。
社交ダンスでは特にラテンダンス(ルンバ・チャチャチャ・サンバなど)を踊る女性(男性もですが)のヒップムーブメントがとても素敵なので、そのヒップアクションを真似したくなりますが、見よう見まねでやると、少々おかしなことになってしまいます。
おかしなというのは、一番肝心なヒップアップが、ヒップバックとも言えそうな、ヒップを上でなく後ろに突き出してしまう格好をしてしまうのです。
ヒップアップは、ヒップの問題ではなく、身体全体の姿勢から生まれるものです。そしてその姿勢の作り方は、まず頭と上体の「ツリ」が一番大切です。
ツリをするためには、まず頭を天井につけるつもりくらいにグーッと上に伸ばします。また頭のてっぺんにヒモをつけて、それを引っ張り上げるような気持ちで、首の後ろをキューッと伸ばします。
そうすると、背骨も伸びて、腰の後ろも伸びて、その結果ヒップアップされた状態になります。
もう一つのコツは、今度は両足のモモから膝をしっかりと伸ばすことです。特に膝が大切で、ダンス用語で「ニー・バック」という言葉がありますが、そもそも前にしか曲がらない膝(ニー)を後(バック)させるとは、これ如何に?と言いたくなりますが、実際、膝を後ろに押し込むことがとても大切です。言い方を変えると、膝の後ろ側をしっかりと伸ばすということになります。
世界のトップラテンダンサーを、身近に何度も見たことがありますが、その両足たるや本当に引き締まって、まるで大理石の彫刻のようでした。
話を戻して、ヒップアップは、先ずは上体をしっかりと伸ばして、首を伸ばす。そして同時に両膝もしっかりと伸ばすこと。これを日常いつも心がけて生活すれば、自然にその為の筋肉がついてきて、同時に必要な部分のストレッチも少しずつされてきて、ある日、若々しいヒップアップされた自分の姿に気がつくでしょう。このことは、私が保証します。
あとは継続は力なり。です。
では-
 社交ダンスでは特にラテンダンス(ルンバ・チャチャチャ・サンバなど)を踊る女性(男性もですが)のヒップムーブメントがとても素敵なので、そのヒップアクションを真似したくなりますが、見よう見まねでやると、少々おかしなことになってしまいます。
社交ダンスでは特にラテンダンス(ルンバ・チャチャチャ・サンバなど)を踊る女性(男性もですが)のヒップムーブメントがとても素敵なので、そのヒップアクションを真似したくなりますが、見よう見まねでやると、少々おかしなことになってしまいます。おかしなというのは、一番肝心なヒップアップが、ヒップバックとも言えそうな、ヒップを上でなく後ろに突き出してしまう格好をしてしまうのです。
ヒップアップは、ヒップの問題ではなく、身体全体の姿勢から生まれるものです。そしてその姿勢の作り方は、まず頭と上体の「ツリ」が一番大切です。
ツリをするためには、まず頭を天井につけるつもりくらいにグーッと上に伸ばします。また頭のてっぺんにヒモをつけて、それを引っ張り上げるような気持ちで、首の後ろをキューッと伸ばします。
そうすると、背骨も伸びて、腰の後ろも伸びて、その結果ヒップアップされた状態になります。
もう一つのコツは、今度は両足のモモから膝をしっかりと伸ばすことです。特に膝が大切で、ダンス用語で「ニー・バック」という言葉がありますが、そもそも前にしか曲がらない膝(ニー)を後(バック)させるとは、これ如何に?と言いたくなりますが、実際、膝を後ろに押し込むことがとても大切です。言い方を変えると、膝の後ろ側をしっかりと伸ばすということになります。
世界のトップラテンダンサーを、身近に何度も見たことがありますが、その両足たるや本当に引き締まって、まるで大理石の彫刻のようでした。
話を戻して、ヒップアップは、先ずは上体をしっかりと伸ばして、首を伸ばす。そして同時に両膝もしっかりと伸ばすこと。これを日常いつも心がけて生活すれば、自然にその為の筋肉がついてきて、同時に必要な部分のストレッチも少しずつされてきて、ある日、若々しいヒップアップされた自分の姿に気がつくでしょう。このことは、私が保証します。
あとは継続は力なり。です。
では-
2011年10月09日
困った人たち
今日は、9月25日の「スローフォックスとクイック ダンスミニ知識」の続編でもあります。「踊りませんか?」の中で、
|モダンの多様なテクニックを一通り消化して初めて、スローフォック
|ス特有のあの軽みと揺れを踊りで表現できるのだ。そのレベルに辿り
|着くまでには、技術はもちろんだが、カップルとして、人間としての
|成熟まで求められるような気がする
とあり、それに続いて今日ご紹介する文章が続きます。読み進んで頂ければ今日のタイトル、「困った人たち」の意味が分かって頂けると思います。少々長いですので、お時間のある時にでもどうぞ。
|ここで我流のダンス道を述べようなどというおこがましいことはしたく
|ない。ただ、こうはなりたくないな、と思うタイプがある。あなたのダ
|ンス教室にも、必ずひとりくらいいるのではないだろうか。こういう人、
|困るのよね、というタイプ。
|
|ダンスのマナーにも通じるものがあるので、5タイプに絞って挙げてみ
|たい。よくよく考えてみると、どれも結局は、ふたりで踊ることを知ら
|ない人たちである。(中略)
|
|そのひとつは、レッスンつけ型タイプ。組んだ相手のダンスを四六時中
|直している。初心者にしてみれば、最初はけっこうありがたい。このタ
|イプは相手に対する優越感が生き甲斐なのかもしれない。一見、親切な
|のだが、自分の方の技量はあまり眼中にない。したり顔で教えてくれて
|いて、実は的がはずれていた、ということもたびたび起こる。
|
|ふたつ目は、文句つけタイプ。とにかく相手の一挙一動に文句をつける。
|自分のことは棚に上げて、あなたがこうするから、ああするからうまく
|いかない。とくる。自分の欠点はどうかというと、とんと見えていない。
|最初のタイプと似ているが、自分がうまく踊りたい一心である。
|
|(浅野素女 著「踊りませんか?」第4章 p.94-95から引用)
ダンスの団体レッスンを受けられた経験があるかたは、そうそうと頷いておられるのではないでしょうか。また、ダンスパーティなどに行った時に、こういう「教え魔」の人もよく見かけますね。
長くなりましたので、残りの3タイプについては、来週ご紹介させて頂きます。
というところで、今日はこの辺で。
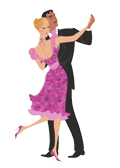
|モダンの多様なテクニックを一通り消化して初めて、スローフォック
|ス特有のあの軽みと揺れを踊りで表現できるのだ。そのレベルに辿り
|着くまでには、技術はもちろんだが、カップルとして、人間としての
|成熟まで求められるような気がする
とあり、それに続いて今日ご紹介する文章が続きます。読み進んで頂ければ今日のタイトル、「困った人たち」の意味が分かって頂けると思います。少々長いですので、お時間のある時にでもどうぞ。
|ここで我流のダンス道を述べようなどというおこがましいことはしたく
|ない。ただ、こうはなりたくないな、と思うタイプがある。あなたのダ
|ンス教室にも、必ずひとりくらいいるのではないだろうか。こういう人、
|困るのよね、というタイプ。
|
|ダンスのマナーにも通じるものがあるので、5タイプに絞って挙げてみ
|たい。よくよく考えてみると、どれも結局は、ふたりで踊ることを知ら
|ない人たちである。(中略)
|
|そのひとつは、レッスンつけ型タイプ。組んだ相手のダンスを四六時中
|直している。初心者にしてみれば、最初はけっこうありがたい。このタ
|イプは相手に対する優越感が生き甲斐なのかもしれない。一見、親切な
|のだが、自分の方の技量はあまり眼中にない。したり顔で教えてくれて
|いて、実は的がはずれていた、ということもたびたび起こる。
|
|ふたつ目は、文句つけタイプ。とにかく相手の一挙一動に文句をつける。
|自分のことは棚に上げて、あなたがこうするから、ああするからうまく
|いかない。とくる。自分の欠点はどうかというと、とんと見えていない。
|最初のタイプと似ているが、自分がうまく踊りたい一心である。
|
|(浅野素女 著「踊りませんか?」第4章 p.94-95から引用)
ダンスの団体レッスンを受けられた経験があるかたは、そうそうと頷いておられるのではないでしょうか。また、ダンスパーティなどに行った時に、こういう「教え魔」の人もよく見かけますね。
長くなりましたので、残りの3タイプについては、来週ご紹介させて頂きます。
というところで、今日はこの辺で。
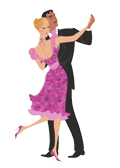
2011年10月06日
人生の季節
今日は、目一杯つれづれ日記ものです。
いつだったか、もうずいぶんと昔に何かの本で読んだことです。
人生には、その時々に季節というものがあって、その季節の時にはその季節に合ったことをしなければいけない。季節が移り変わって、あとからそのことをやろうとしても、それは季節はずれになってしまう…と。
人生には、幼少期、少年期、青年期、壮年期、熟年期、晩年期とでもいう季節があって、それぞれの季節には、それぞれの季節の時にやらなければならない、やった方が良いことがある。
先の文章を私が読んだのは、青年期の頃だったと記憶しています。それを読んで心に何か感じるものがあって、そのことはその後の人生の折々に思いだし、そして最近またこの言葉が蘇ってきています。
やりたい、やらなければ、でも…、ということが人生では多いような気もします。でも…の後に続くことは、その時々で異なっていたでしょうが、振り返ってみると、「今のこの季節の時にこのことをやっておかないと、あとでは季節はずれになってしまう」ということを、しっかりと自分に言い聞かせることができれば、もっと思い切った選択や行動が取れたのではということもありました。
過ぎ去った時は帰って来ない。であれば、今日からもう一度、今の季節にできること、この季節に似合った行動を取って生きて行きたいと思っています。

いつだったか、もうずいぶんと昔に何かの本で読んだことです。
人生には、その時々に季節というものがあって、その季節の時にはその季節に合ったことをしなければいけない。季節が移り変わって、あとからそのことをやろうとしても、それは季節はずれになってしまう…と。
人生には、幼少期、少年期、青年期、壮年期、熟年期、晩年期とでもいう季節があって、それぞれの季節には、それぞれの季節の時にやらなければならない、やった方が良いことがある。
先の文章を私が読んだのは、青年期の頃だったと記憶しています。それを読んで心に何か感じるものがあって、そのことはその後の人生の折々に思いだし、そして最近またこの言葉が蘇ってきています。
やりたい、やらなければ、でも…、ということが人生では多いような気もします。でも…の後に続くことは、その時々で異なっていたでしょうが、振り返ってみると、「今のこの季節の時にこのことをやっておかないと、あとでは季節はずれになってしまう」ということを、しっかりと自分に言い聞かせることができれば、もっと思い切った選択や行動が取れたのではということもありました。
過ぎ去った時は帰って来ない。であれば、今日からもう一度、今の季節にできること、この季節に似合った行動を取って生きて行きたいと思っています。